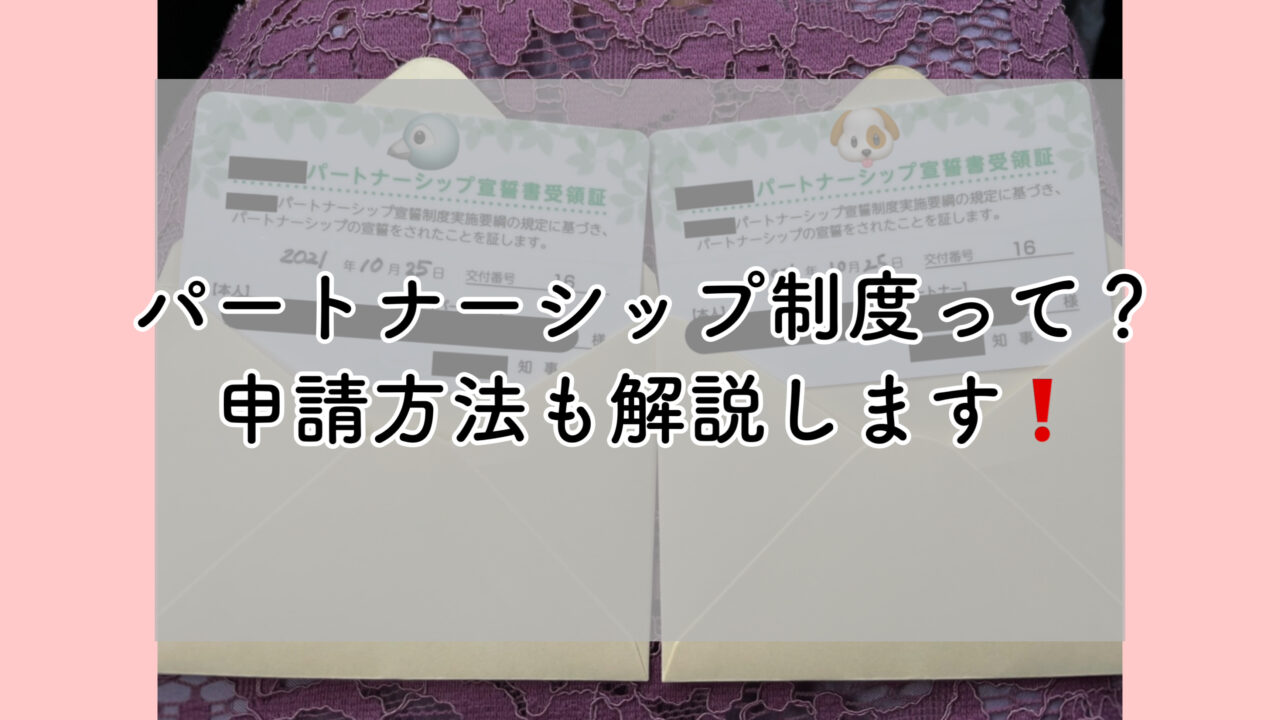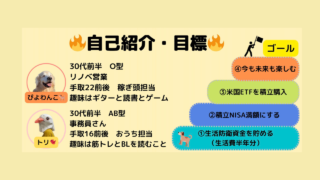こんばんは、ぴよわんこです。
5月の割には暑かったり寒かったりの気温差に体がついていかなくなりそうですが皆さんはいかがお過ごしですか?
さてさて。
私とトリ
この制度を活用することで得られるメリットや証明できることがいくつかあるのですが私の周りのセクシャルマイノリティの知人は、利用していない人がほとんど…
また、申請をしてから半年以上経過して実際にどんなメリットがあるのかも理解できたように思うので
今回は
- パートナーシップ制度って?
- どこで申請できる?
- メリット、デメリットは?
- パートナーシップ制度の課題は?
- 申請方法
これらについて解説していきたいと思います
申請を検討されている方やそんな制度があるんだ!と興味を持った方、すでに申請をされている方も!ぜひご覧くださいませ
最後に実際に利用してみた感想もお伝えしますね♪
パートナーシップ制度って?
日本では現状、2番目に婚姻に近い制度

パートナーシップ制度とは各県の言い方を参照するとこんな感じ。
パートナーシップ宣誓制度とは、お互いを人生のパートナーとし、日常の生活において相互に協力し合うことを宣誓したお二人(一方又は双方が性的少数者)に対して、県が宣誓書受領証等を交付する制度です。
つまり市町村、都道府県に対して「私達は夫婦同様に世帯を共にしてます!家族です!」というお墨付きをもらうようなイメージですね。
どんな制度?
この制度に申請し、交付してもらうことで法的効力はないものの一般的な婚姻関係を結んでいるご夫婦が利用できるいくつかの行政のサービスを受けることができたり、賛同している民間サービスを利用することができるようになります。
ちなみに法的効力もある方法を選択するなら「公正証書を作成すること」と「養子縁組をする」という方法がありますが…
- 公正証書を作成…公証人が必要 費用が結構掛かる(公正証書作成代は1万1000円)
- 養子縁組…法律上は養親と養子、親子になってしまう
結婚とはこのなるニュアンスを含む関係になってしまうか、日本における結婚と同程度の保証が受けられるわけではない、というのが現状ですね。
どの地域が対象?

この制度は県として導入している地域と、市町村単位で導入している場合と二通りあります。県として導入しているところを例に上げると…
- 大阪府(2020年1月)
- 青森県(2022年2月)
- 秋田県(2022年4月)
- 茨城県(2019年7月)
- 群馬県(2020年12月)
- 三重県(2021年9月)
- 福岡県(2022年4月)
- 佐賀県(2021年8月)
渋谷区と世田谷区で2015年11月5日に、日本で初めてのパートナーシップ制度が発足されたそうです。当時ニュースで話題になっていたのを覚えています。
でも、東京が都全体として導入しているわけではないと思うと意外に感じますね
地町村単位は同性婚実現に向けて活動をされている「MarriageForAllJapan」さんのHP(https://www.marriageforall.jp/)をご確認いただくと自分の住む地域が該当しているか確認することができます
どこでできる?
市町村単位で導入されている地域なら市役所、都道府県単位なら県庁にて受付しています。
ちなみに平日の9時〜17時までの受付時間がほとんど。
後述しますが書類や予約などの事前準備が必要なため婚姻届のようにいつ行っても受付してもらえるわけではないのでご注意くださいね。
メリットは?
そんな背景を持つパートナーシップ制度ですが、こちらを利用することでこのようなメリットがあります。こちらは私の住む地域でできますよ!と説明いただいたものです。
- 公営住宅の入居申し込みができる
- 賃貸の入居時に家族として扱ってもらえる
- 病院に付き添うことができる(通常は他人なので緊急時に病室に中に入れません)
- 生活保護制度を利用する際、同一世帯扱いになる
- 住宅ローンが組める(私の地域は地方銀行のみでした)
- 養育里親に登録できる
- 携帯電話の家族割が適応できる(NTT、ドコモ、au、ソフトバンクなど)
- 生命保険や損害保険の受取人になれる(東京海上日動火災、損害保険ジャパンなど)
- クレジットカードの家族カードが申し込める(楽天やオリコカードなど)
- 要介護認定申請をパートナーが代理で申請できる
私がトリとの生活の中で心配だな…と思っていたものはもしものときの病院の付添いや年老いてからの介護申請だったので、パートナーシップ制度を結んだときはこのようなメリットのお陰で少し安心して暮らしていけるなァ・・と感じましたね。
デメリットはある?
逆に自身が感じたり、一般的に言われるようなデメリットはこんな感じ。
- 役所の人にセクシャルマイノリティだとバレる
- 申請が少し面倒(事前予約がいるなど)
- 法的効力はないので絶対にこの制度が守られるとは限らない
- 制度を結ぶことによる制限(結婚に親しい約束、なのでそれ相応の制限はあります)
- パートナーシップ制度を結んでいなかったとしても、なんとかなることもある
申請をして受理される際は市町村もしくは都道府県の職員さんに手続きをしてもらうことになるので、「完全に秘密にしておきたい…
自民党県議が同性カップル住所を無断公開、「アウティング」禁じる条例施行の三重県で
三重県議会の小林貴虎県議(47)=自民党県議団=が、自身に公開質問状を送ってきた同県伊賀市の男性カップルの氏名と住所を、無断でブログに公開していたことが5日、分かった。三重県は性的指向や性自認を第三者に暴露する「アウティング」を禁止する都道府県としては初の条例を、1日に施行したばかり。
2021年4月5日 東京新聞
私も実生活の中では親しい人物にしか同性愛者であることはカミングアウトしていないのでこんな目にあったらたまったもんではないと思います…。
なんとかなる、については…
現在賃貸の住宅に住んでいますが「ルームシェア可」の物件ではなくとも、ふつーに借りることができて特に困らなかったことと、トリが入院をした際に気を使っていただけていたのか病室に入ることができたので、地域や人によっては、そういったものに困らないのかも知れません。
パートナーシップ制度の課題
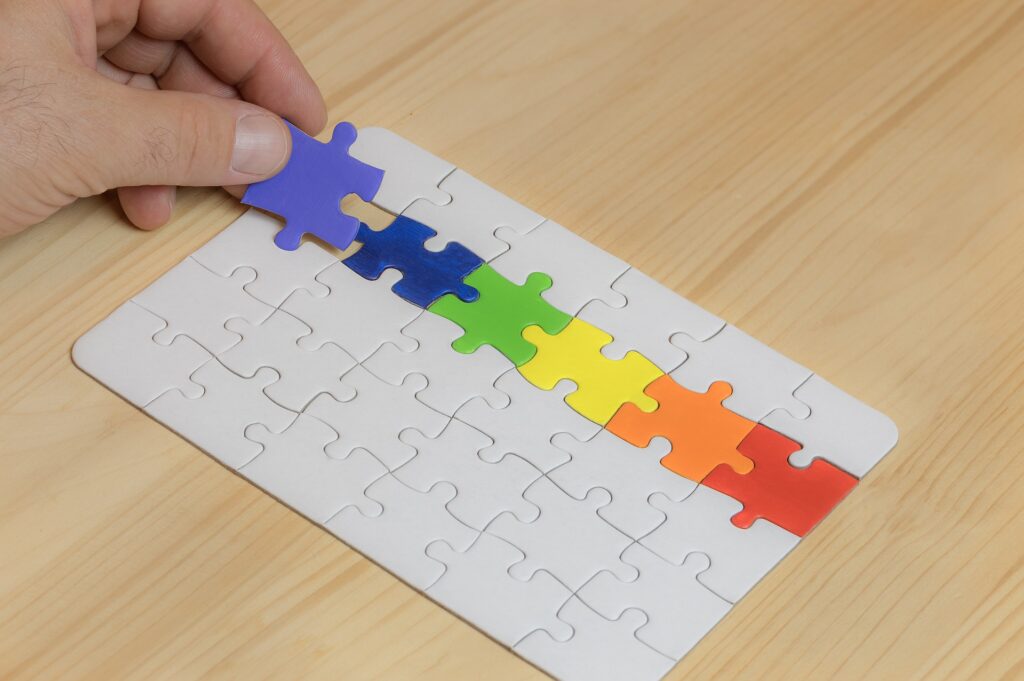
完全な婚姻関係の代わりとはいえない
前述の通り完全に結婚と同等の権利を享受できる制度ではないので、利用されている方が少ないのも納得です。
また、法的効力はありませんし、実施している市町村、都道府県から引っ越しをしてしまえばこのパートナーシップ制度で結んだ関係は解消となってしまいます。
でも…普及していけば同性婚への一歩になるかも!
ただ、これは私の一意見になりますが…
こういったものもいろんな聞き取りをしてわざわざ準備してくれている制度なわけで、足りないからとだれも使わない状態になれば「なんだ、準備してみたけど使う人がいないならそもそもセクシャルマイノリティ(性的少数者)なんていないのでは?」とか「こんなに利用者が少ないのなら制度は撤廃、同性婚合法化もしなくていいでしょ」なーんて意見に転がってしまうんじゃ…と想像してしまうわけです。
そう行った事態にならないように「ここにいますよ−!」と制度を利用して少しだけ行政に声を上げることで、一番の理想である一般的な結婚と同じ制度がいつか(できれば老後に間に合うくらいに)合法化されていけばいいなぁ…とも思っています。
申請方法

いろいろとご説明したパートナーシップ制度ですが、実際に申請をする際はどういった準備が必要だったかを解説していきます。
前日までの事前準備
①市町村、都道府県の担当部署に申請の予約をする
まずは自身の住む地域の担当部署を確認して「パートナーシップ制度の宣誓をしたいのですが…」とお電話しましょう。このときに
- 宣誓する日時
- 場所
- 必要書類
これらの説明を受けるので忘れないようメモを取っておきましょう。
また、事前にパートナーと平日一緒に手続きに行ける日にちを確認しておくをスムーズに予約できると思います
②書類を準備する
必要書類はこんな感じ。
例は大阪市ですが、私の住む地方も同じ準備物でした。
提出書類
①住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書又は戸籍の附票の写し
②独身証明書、戸籍個人事項証明書等、現に婚姻をしていないことを証明する書類提示書類
大阪市パートナーシップ
①個人番号カード(マイナンバーカード)
②旅券(パスポート)
③運転免許証
④その他官公署が発行した免許証、許可証又は登録証明書等であって、本人の顔写真が貼付されたもの。
余談になりますが、私は独身証明書は事前に区役所で発行してもらっていましたが、住民票の写しをすっかり忘れていて宣誓中に発覚。
慌てて宣誓途中で抜け出して、役所内のコンビニのプリンターで発行しました
マイナンバーカードを作っていて…ほんとに良かったです
申請日当日
①市町村役所、もしくは県庁に向かう
あとは約束した時間に必要書類を持って役所に向かうだけ。
私達の場合は、受付に声をかけなくて言いようにか事前に個室の場所を指定されそこに案内されました。
②申請内容、受けられるサービスの説明を受けて書類にサインする
あとはいろんなサービス内容を確認したり、お互いの意思を確認されたり…あれよあれよと進んでいき、合計30分ほどで申請は完了します。
場所によっては宣誓書と宣誓カードがもらえるようですが、私達の地域では以下のカードのみ頂きました。
私達の宣誓の時は、最後に職員さん方が「おめでとうございます!」とお祝いしてくださったり、記念写真を取ってくれたり「どうしてこの制度を利用しようと思いましたか?」などいくつか質問を受けたりしましたね。
実際に申請してみて…

申請してみた感想としては…なんだかあっけないくらいにさくっと終わったなという感覚と少し「世の中に認められた」ような気持ちになったように思います。
また、事前にパートナーシップ制度について情報収集していた段階では
宣誓する際はお互いの愛の証明を職員に提示しなくてはならないらしいと聞いており(伊賀の情報だったかな?)公衆の面前で、しかもお硬いであろう役所の職員さんの前でどうやって証明するの…?キスでもするの…?嫌すぎる…!
と話していたのですがそういった条件はまったくなかったのでそういった面でも安心しましたね
もし、なにか証明を求められた方がいらっしゃったら教えてください
まとめ

いかがでしたか?
少し長い記事になってしまいましたがパートナーシップ制度が気になっていた方の参考になっていれば嬉しく思います。
私は人に恵まれたからか運がいいのか、私自身がセクシャルマイノリティ(性的少数者)だったからといって、ひどい差別やつらい思いをした経験はありません。
なので本来ならばいろいろな権利を主張していくのも大切かも知れませんが、私はなんとなくふわっと受け入れてもらえている今の状態でも構わないと思っています。
現状の日本に思うところはあれど、国外へ飛び出てやる
だからこそ、今ある制度はしっかり利用した上でこういった記事を作成したり、SNSなどでも自分なりに発信をしていけたらと思っているので、見守っていただけますと幸いです。
それでは今日もご覧いただきありがとうございました。
「今も未来も豊かな暮らし」を一緒に実現していきましょう!